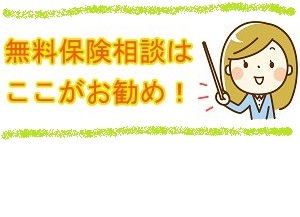学資保険に加入する際に「どのような内容で契約すべきか」「保険期間はどのくらいが良いのか」「祝金の有り無しはどちらが良いのか」などの疑問が出てくるかと思います。
それらの疑問は保険を契約する前に必ず解決しておくべきです。このページでは学資保険に加入する際に迷うであろう疑問点をピックアップして簡潔に答えを出していますので、保険相談を受けた後、または学資保険に加入する前の最終確認として出来れば読んでおいてもらえれば幸いです。
このページの中身
■目次
終身保険との比較
学資保険を選ぶ際、保険相談などでよく比較に出されるのが終身保険です。どちらを利用すべきか迷う方も多いですので、ここでしっかりチェックしておきましょう。
学資保険と終身保険はどちらに加入すべきか
保険相談をした方の中には「学資保険よりも終身保険の方が良いですよ」とFP(相談員)に言われた方もいるかも知れません。
これ、最近はとてもよくある話なのですが、実は学資保険の方が手数料が少ない(売ってもあまりFPの利益にならない)ため、できれば手数料の高い終身保険を売りたくて勧めているだけなのです。
つまり、FPの方が終身保険の方を勧めるからといって、学資保険の方が劣っているわけではないのです。学資保険を検討するにあたり、そのことは最初に知っておいてください。
学資保険と終身保険は確かに「子供の学費を用意できる保険」という点では似ていますが、保障内容はかなり異なります。
学資保険は基本的に満期が決まっており、期限がくると強制的に全額受け取りになります。その代わり、同じ保険期間の終身保険と比べると返戻率(受け取れるお金)は少し高めに設定されています。
対して終身保険は満期が決まっていないので、もし大学入学費用を貯蓄で賄えた場合はずっと据え置くことができます。据え置くことで返戻率は少しずつUPしていくので、この点がメリットです。ですが、学資保険を検討する方は大学費用を保険商品で貯めることを想定してきているため、終身保険が持つ「満期がない」というメリットを活かせる家庭は限られてしまいます。
2つの保険のそのような特性から、家庭の状況によってどちらを選ぶかを変えるのが良いかと思います。
| 学資保険を選ぶべき状況 |
|
|---|---|
| 終身保険を選ぶべき状況 |
|
学資保険の選び方、保障内容についての疑問
学資保険は具体的にどのように選べば良いのか、そして保障内容はどうすべきかの解説をしています。学資保険の選び方を知るために、ここはチェックしておいてください。
学資保険は返戻率の高さで決まる
学資保険は貯蓄型の保険商品のため、返戻率が高ければ高いほど優秀な商品という特徴を持っています。
例えばある学資保険に加入し、18年間で100万円の保険料を支払い、学資金としてトータルで110万円を受け取った場合の返戻率は110%となります。(現在はマイナス金利の影響で、110%を超える学資保険はなかなかありませんが・・)
これが学資金が115万円受け取れる場合は返戻率が115%となり、先ほどの110%よりも優秀となります。基本的には返戻率が高ければ高いほど、私たちはより多くのお金を受け取ることが出来るということになるのですね。
この返戻率は会社ごと、そしてプランごとに異なりますので、優秀な学資保険を探す場合は各商品を出来るだけ同条件にしてから比較する必要があります。そこで返戻率が一番高いところが、最も加入する価値がある優秀な学資保険ということになるのです。
また、返戻率はすでに全てが決まっている訳ではなく、実は私たちの選択次第で返戻率を上げた状態で契約することも出来るのです。
返戻率を上げる方法についてはこちらで触れていますので、興味がある方は先に読んでみても良いかと思います。
受取総額と保険料の基準はいくら?
大学の入学金と授業料を合わせた場合、一般的には国立大で80万円前後、私立大で120万円~150万円くらいになると言われています。(医学部などはさらに高いため、この例には含まれていません)
これに加えて通学のために一人暮らしをする場合は、さらに新生活のための家財道具の購入・引越し費用まで負担する必要があり、この費用だけで40万円くらいかかってしまいます。
このことから、もし子供が自宅通学が不可能な地域の大学に合格した場合、国立大学で120万円、私立大学で160万円~190万円くらい入学時に必要になってしまうのです。
そのため、17歳または18歳で満期金を200万円くらい受け取れるようになれば十分に対応できるかと思います。余裕を持って300万円といったところですが、家計が厳しい場合は200万円にしておくと良いでしょう。
また、受取総額(満期金と祝金の合計額)を200万円とした場合、保険料は1万円くらいになります。返戻率が高い10歳払にした場合でも月々1万5千円くらいなため、学資保険の月々の保険料としては1万円~1万5千円くらいが妥当なところだと言えるでしょう。
学資金の受取年齢はいつが良いのか
学資保険に加入する際、学資金(満期金)の受取年齢をいつにするか迷ってしまうかと思います。
これについては、経済的に余裕があるなら子供が22歳の時に受け取り(満期)でも良いかと思います。運用期間が長期になるほど返戻率は高くなってくれますので、大学の入学費用が貯蓄で払えるのであれば22歳満期にしておいた方が最終的にお得になります。
ですが、ほとんどの家庭の場合は大学入学時の入学金や授業料に使いたいと考えていることでしょう。その場合は17歳もしくは18歳に満期金を受け取る設定にするのがお勧めです。
幼稚園・小・中・高校の入学のタイミングで祝金を受け取るプランもありますが、途中で祝金を受け取る場合は最終的な返戻率が下がってしまうため、できれば17歳・18歳のタイミングで一気に受け取ってしまうのが良いかと思います。(家計が厳しい場合は小・中・高校の入学金で祝金を貰うプランにした方が安心です)
ただし、注意点が一つあります。子供が生まれた月や学資保険を契約した月によっては、18歳満期にしてしまうと入学金や授業料を支払う大事な時までに満期金を受け取ることができない・・という可能性が出てしまうのです。
そのため、17歳満期が良いか、それとも18歳満期が良いのかはそれぞれの家庭・子供ごとで異なってきてしまいます。以下の表で簡単にまとめていますが、確実を期すために満期金の時期設定はFPと相談の上で決めるのが良いかと思います。
【18歳満期で契約した場合】
| 誕生日 | 契約月 | 満期月 | 入学金・授業料の 支払いに間に合うか |
|---|---|---|---|
| 5月15日 | 7月 | 高校3年の7月 | 間に合う |
| 9月15日 | 7月 | 大学1年の7月 | 間に合わない |
| 1月15日 | 2月 | 高校3年の2月 | 間に合う (試験日による) |
【17歳満期で契約した場合】
| 誕生日 | 契約月 | 満期月 | 入学金・授業料の 支払いに間に合うか |
|---|---|---|---|
| 5月15日 | 7月 | 高校2年の7月 | 間に合う |
| 9月15日 | 7月 | 高校3年の7月 | 間に合う |
| 1月15日 | 2月 | 高校2年の2月 | 間に合う |
祝金ありとなしではどちらを選ぶべきか
学資保険には満期に一括で学資金を受け取るプランもあれば、幼稚園・小・中・高校の入学時に少しずつ祝金を受け取るというプランもあります。
どちらを選ぶべきか迷いどころではありますが、学資保険は基本的に長い期間運用した方が返戻率が高くなるため、大学入学時までは貯蓄だけで何とかなるという経済状態の場合は満期一括受取にした方が返戻率が高く、お得になります。
そのため、経済的にある程度余裕があり、小学校・中学校・高校では何とか貯蓄だけで足りそうな場合は、17歳満期または18歳満期の祝金なしのプランで契約するのが良いかと思います。
ただ、家計によっては中学校や高校あたりで祝金が欲しい・・という状況も十分にありえます。確かに学資保険は返戻率が高ければ高いほど魅力ではありますが、必要な時に必要な金額を受け取れないなら保険としての意味は薄れてしまいますので、経済状況が厳しいご家庭では祝金ありにしても全然いいと思っています。
学資保険の契約者は夫が良い?それとも専業主婦の妻?
学資保険は男性よりも女性の方が返戻率が少し高いため、奥さん(専業主婦)を契約者にした方が良いのでは?と考える人も多いです。
これは確かに返戻率という面だけみると奥さんの方がほんの少しだけお得になるのですが、奥さんを契約者にすると一つ問題が生じてしまいます。
その問題とは、「大黒柱の死亡時に保険料払込免除が適用されなくなる」という点です。
通常の学資保険では契約者が死亡(または高度障害)した場合は以後の保険料の払込が免除されるようになっています。それにより、契約者が旦那さんの場合は旦那の死亡により以後の保険料を支払う必要がなくなるのです。これが保険料払込免除という制度です。
ですが、奥さんを契約者にしてしまった場合、旦那さんは契約者ではないので、もし旦那さんが死亡(または高度障害)した場合は以後の保険料の払込は免除されないのです。専業主婦(またはパートなどの低所得者)にとっては、大黒柱を失っているのにさらに保険料の払込が免除されないというのは、かなりの経済的ダメージになるかと思います・・。
そのため、基本的には夫の方を契約者にしておくことをお勧めします。ほんの少しだけ返戻率は高くなりますが、保険料払込免除の保障を活かす方が重要ですので。
ちなみに、夫婦共働きで収入がほぼ同じか、もしくは奥さんの方が収入が上の場合は奥さんが契約した方が良いかと思います。どちらが亡くなっても家計へのダメージは同じなので、返戻率が高い方で契約するのが良いでしょう。ただし、年齢が低い方が返戻率が高くなるので、姉さん女房の場合はお互いの返戻率を比較してみて、高い方を選ぶのが良いかと思います。
医療特約は付けるべき?
学資保険の中には医療特約を用意している商品もあります。これは子供の病気やケガに備えることができるものなのですが、この特約を付けるべきかで悩む方もいらっしゃいます。
これについては、学資保険に子供用の医療特約は付けなくても良いというのが個人的な意見です。現在の日本の各自治体では子供の医療費をカバーしてくれるところが多くなっており、地域によっては子供の医療費については無償としているところもあります。
そのため、付加したとしても役に立つことは少なく、無駄な保険料をずっと払い続けることになりかねません。
そもそも学資保険は貯蓄のために加入するものであり、わざわざ役に立つかどうかかなり微妙な医療特約を付けて、余計な保険料を支払って返戻率を下げる必要は全くないと言えるでしょう。
ちなみに、たまに医療特約が自動でセットされている学資保険もありますが、そのような学資保険は最初から選ばない方が無難かと思います。
贈与税がかからないように受取人を設定しよう
学資保険を契約する際に、「この子の学資金だから」という親心から満期金の受取人を子供にしたいという方も見かけます。
ですが、ハッキリいって学資保険の受取人を子供にするのは辞めておいた方が良いです。なぜかというと、受取人を子供にすることで贈与税がかかるようになり、税金を多くとられてしまうことになるからです。
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 | |
|---|---|---|---|---|
| 父または母 | 子ども | 契約者と同一 | 所得税 | 一時金・・一時所得 |
| 年金(分割)・・雑所得 | ||||
| 父または母 | 子ども | 子ども | 贈与税 | |
この表を見ると分かりますが、契約者(保険料を支払う人)は父親か母親のどちらかとなるでしょう。そして被保険者は子供となります。
そして受取人を父親または母親(契約者と同一)にすることで所得税となり、満期金や祝金を一時金で受け取った際は一時所得がかかるようになります。
一時所得であれば50万円までの特別控除が利用できるため、200万円~300万円程度の学資金受取であれば税金がかかることはほぼありません。
反対に、受取人を子供にすると贈与税がかかるようになります。例えば200万円の満期金を受け取った際、贈与税だと9万円ほど取られてしまいます。
一時所得であれば取られることのない税金が、贈与税だと9万円も取られてしまうのです。これはかなりもったいないと言えますね。
そのため、基本的には契約者と受取人は同一人物にしておき、父か母のどちらかで契約するのが最もいい方法となります。また、受け取る際は年期ではなく、一時金として受け取ることをお勧めします。
返戻率を上げるための方法とは
学資保険を選ぶうえでとても重要な判断基準となるのが「返戻率」です。この返戻率が高ければ高いほどお勧めの商品となり、契約する価値がある学資保険となります。
そんな大注目の返戻率ですが、実は自分たちの選択や年齢により、返戻率は上がったり下がったりします。
このページでも女性が契約者になる(この選択は注意が必要です⇒詳しくはこちら)方法や、祝金を無しにする、学資金の受取時期を後の方にするといった方法で返戻率を上げることが可能と書いていますが、他にもいくつか方法があります。
- 保険料の支払いを月払ではなく、半年払や年払にする
- 保険料の払込期間を短くする(18歳満期だけど保険料の払込は10歳までなど)
- 契約者や子供の年齢が低い方が返戻率が高いため、子供が生まれたら早めに契約する
- クレジットカード払にしてポイント還元
年払にする、保険料の払込期間を短くするといった方法はある程度まとまったお金がないとできない方法ですので、誰にでもできるという訳ではないです。ですが、もし出来るのであればかなり返戻率は高くなるので、まとまったお金を出せる方は覚えておくと良いでしょう。
保険料の支払いをクレジットカード払にするのも良い方法です。年会費無料のクレジットカードでも還元率は1%前後はあるため、実質的に返戻率が1%前後高くなってくれます。この中では最も簡単な方法ですので、少しでもお得に契約したい場合はクレジットカード払にすると良いでしょう。ただし、クレジットカード払ができない保険会社もあります。
ちなみに、管理人のお勧めは還元率1%の楽天カードです。私は支払いの大部分を楽天カードにしているため、楽天市場のポイントがかなり貯まってくれます。
年会費無料系の中ではとてもお勧めのカードですので、興味がある方は作ってみてはどうかと思います。
学資保険を契約する際に知っておきたい予備知識
学資保険に加入すれば大学4年間の学費は足りるのか?
「受取総額と保険料の基準はいくら?」の部分で、学資金の受取総額は200万円~300万円くらいを推奨と解説していますが、これはあくまでも大学入学時に必要となる金額です。
当然ですが大学は4年制(医学部は6年制)ですので、大学の4年間の学費・生活費は合計500万円~650万円くらいはかかってしまいます。私立大学で仕送りをしている場合は1,000万円前後かかってしまうことも普通にあります。
この金額を学資保険だけで備えるのは無理があります。そのため、足りない分は自分たちで貯蓄していくか、それでも足りない場合は奨学金や教育ローンに頼るという方法も検討する必要がでてくるかも知れません。
奨学金や教育ローンはいわゆる借金ですのでそれぞれに注意すべき点はありますが、両方とも学生の味方に間違いはありませんので、メリットとデメリットをよく理解した上で利用を検討してみるのも良いかと思います。
また、本当に家計が厳しい場合は子供にアルバイトをしてもらうのもお勧めだと思います。若いうちから仕事を頑張ったり、仕事を通じて人と人との繋がりを学ぶことは今後の人生の大きな糧となるはずですので、是非ともアルバイトで社会経験を積んで給料をもらってきて欲しいなと思います。
学資保険に加入できないケースとは
学資保険は子供が生まれた時には検討しておきたい保険の一つではありますが、人によっては加入が難しい場合があります。
以下のようなケースでは加入が難しくなってしまいますので、該当する方は注意しておいてください。
ケース.1 契約者が持病を持っている
契約者が持病を持っている場合、基本的には加入することができなくなります。
ケース.2 契約者がすでに高齢
学資保険は商品によって加入年齢の範囲が異なりますが、大体18歳~60歳くらいとなっています。商品によっては45歳までとなっているものもあります。
高齢出産で生まれた場合や、祖父・祖母が契約者となって加入することを検討している場合は、年齢オーバーにより加入することができなくなってしまいます。
ケース.3 子どもが大きくなっている
被保険者である子供が大きくなっている場合も加入できないことがあります。学資保険では子供の年齢上限を6歳程度に設定していることが一般的ですので、この年齢を超える前に加入する必要があります。
生命保険料控除の対象になる
学資保険は生命保険料控除の対象になるの?と疑問に思っている方もいますが、学資保険は生命保険の括りのため、問題なく生命保険料控除を利用することができます。
基本的には支払った保険料に応じて所得から控除されます。所得税は最高4万円(旧契約は5万円)、住民税は最高2.8万円(旧契約3.5万円)までが年間の所得から控除されます。
ちなみに、旧契約とは平成23年12月以前に契約したものをいい、それまでに学資保険に加入している方は最高で5万円(住民税は3.5万円)が控除されますが、今から学資保険に加入する場合は新契約となりますので、最高で4万円(住民税は2.8万円)までの控除となります。
生命保険料控除は節税が出来るというかなりお得な制度のため、必ず利用するようにしましょう。サラリーマンの方は会社で年末調整してくれますので、「給与所得者の保険料控除等申告書への記入」や「生命保険料控除証明書の提出」などは忘れないようにしてください。
今検討中の学資保険が正解か分からない方へ(学資保険ランキングのご紹介)
現在、加入しようと思っている学資保険が本当に正解なのか、疑問に思っている方も少なくないでしょう。
そのような方は当サイトの学資保険お勧めランキングを一度みていただけたらと思います。現役FPであり、保険の専門家でもある管理人takaが自信を持ってお勧めしている学資保険をご紹介していますので、学資保険選びで悩む方には参考になるのではないかと思っています。
良ければ是非ともチェックしてみてください。
保険初心者がベストな保険を探すための5つのステップ
- [ステップ.1] 保険は本当に必要なのか
- [ステップ.2] 生命保険の選び方
- [ステップ.3] 最新の生命保険ランキングTOP3
- [ステップ.4] 保険はどこから、誰から加入すべき?お勧め保険相談4選
- 保険相談前に読んで欲しい「生命保険・医療保険の基礎知識」
- [4-1] 最低限の基礎知識
- [4-2] 基本的な保険用語
- [4-3] 加入してはいけないダメ保険とは
- [4-4] 必ず把握しておきたい公的保障4選
- [4-5] 医療保険とがん保険、入るならどっち?
- [4-6] 医療保険とがん保険のベストな組み合わせ3選
- [4-7] 保険加入を期に健康的な生活を送ろう
- [ステップ.5] 保険相談の当日~その後に取るべき行動とは
- 契約前にチェックすべき「解決すべき疑問点」
- [5-1] 定期保険の選び方と疑問点
- [5-2] 収入保障保険の選び方と疑問点
- [5-3] 終身保険の選び方と疑問点
- [5-4] 学資保険の選び方と疑問点 ←今ここ
- [5-5] 個人年金保険の選び方と疑問点
- [5-6] 医療保険の選び方と疑問点
- [5-7] がん保険の選び方と疑問点
興味があるところだけを読んでも良いですが、保険初心者の方は出来るだけステップ.1から順番に読んでもらえればと思います。
この記事を書いた人
- taka

- 当サイト「takaの保険節約術」運営者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者。骨折&手術で身をもって保険の大切さを知って以降、独学で身に付けた保険の知識を紹介するようになりました。FPから紹介された保険の見直しもやってます。保険だけでなく安定度の高い資産運用方法を常に模索しています。ラーメン、焼肉、ラケットスポーツ好き。
保険契約を検討される際には、契約概要を必ずご確認下さい。
保険を探している方はこちらへどうぞ
スポンサーリンク